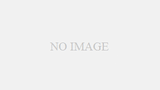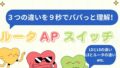【9秒チャレンジ】
BSSは無線LANの最小単位で、1台のAPを中心としたインフラモードや端末同士で直接通信するアドホックモードがあります。一方、ESSは複数のBSSをDSやWDSで接続し、広範囲をカバーする大規模ネットワークで、SSIDを用いて識別されます。
更に詳しく知りたい場合↓
無線LANセグメントのBSSとESSについて
無線LANのセグメントは大きく2つに大別されます。それがBSS (Basic Service Set) と ESS (Extended Service Set) です。
1. BSS (Basic Service Set)
1-1. 定義
BSSは無線LANの最小単位のセグメントです。BSSは48ビットの識別子であるBSSIDによって識別されます。そしてBSSには2つの種類があります。
- インフラストラクチャモード (Infrastructure Mode)
- アドホックモード (AdHoc Mode)
1-2. インフラストラクチャモード
1台のアクセスポイント (AP) を介して構成されるセグメント(BSS)です。クライアント同士はAPを経由して通信します。また、その際に
特徴:
- APが無線通信を管理し、端末同士のデータ転送を制御します。
- 複数の端末が同一のAPに接続することでネットワークを構成します。
- BSSID (BSS識別子): APのMACアドレスがBSSIDとして使用されます。
1-3. アドホックモード (AdHoc Mode)
APを使用せず、端末同士が直接通信して構成されるセグメント(BSS)です。このBSSはIBSS (Independent BSS) とも呼ばれます。
特徴:
- APを使用しないため、端末同士が独立して相互接続します。
- 小規模かつ一時的なネットワーク構成に適しています。
- BSSID: アドホックモードの場合、ネットワークごとにランダムに生成されるMACアドレスがBSSIDとして割り当てられます。
2. ESS (Extended Service Set)
2-1. 定義
ESSは複数のBSSを連携させて構成される大規模無線LANネットワークです。異なるBSS間でAP同士を接続し、端末がシームレスに移動できるようにします。
2-2. 構成要素
- 複数のAP (アクセスポイント)
- DS (Distribution System): BSS同士を接続するシステム。通常、有線LANで接続されますが、無線接続 (WDS) も可能です。
- ESSID (SSID): ESS全体の識別子です。SSID (Service Set Identifier) とも呼ばれ、ESSの識別に使われます。

ESSの識別子であるESSIDは、SSIDと呼ばれることが多いです。
SSIDの特徴:
- 最大32文字の英数字で構成される。
- 同じSSIDを持つAPは同一のESSに属します。
2-3. ESSの役割と特徴
- 複数のAPでエリアをカバー
- 広い範囲で無線LAN接続を提供できます。
- シームレスな接続 (ローミング)
- クライアント端末はBSS間を移動する際に、最適なAPに接続先を自動で切り替えます。
- DS (Distribution System):
- BSS同士を接続する有線LAN (通常のDS) や、無線LAN (WDS: Wireless DS) により、BSS間を中継します。
3. BSSとESSの比較まとめ
| 項目 | BSS (Basic Service Set) | ESS (Extended Service Set) |
|---|---|---|
| 定義 | 最小単位の無線LANネットワーク | 複数のBSSを連携させた大規模な無線LANネットワーク |
| 構成 | 1つのAP または AdHoc (IBSS) | 複数のAP + DS (Distribution System) |
| モード | インフラストラクチャモード / AdHocモード | インフラストラクチャモードのみ |
| BSSID (識別子) | APのMACアドレス (インフラ) またはランダムMAC (IBSS) | – |
| ESSID(SSID) | – | 複数のBSSをまとめる識別子 |
| 使用範囲 | 小規模なエリア | 広域エリア・大規模エリア |
| ローミング | 不可 | 可能 (AP間でシームレス接続) |
6. まとめ
無線LANのセグメント構成は、BSS (Basic Service Set) と ESS (Extended Service Set) という2つの概念に基づいています。BSSは無線LANネットワークの最小単位を指し、単一のアクセスポイント (AP) または端末間で通信が行われる仕組みを表します。BSSには、インフラストラクチャモードとアドホックモードという2つの構成があります。
インフラストラクチャモードでは、1台のAPを中心に構成されたネットワークがBSSと呼ばれます。この場合、APはクライアント端末間のデータ転送を制御し、ネットワーク全体を管理します。APには固有のMACアドレスがあり、このMACアドレスがBSSID (BSS識別子) として使用されます。BSSIDは48ビットの長さを持ち、BSSを一意に識別するためのものです。一方、アドホックモードでは、APを使わずに端末同士が直接通信を行いネットワークを形成します。この構成はIBSS (Independent Basic Service Set) とも呼ばれ、特定の管理者を持たない一時的な小規模ネットワークに適しています。IBSSでは、ランダムに生成されるMACアドレスがBSSIDとして割り当てられるため、インフラストラクチャモードとは異なる識別方法となります。
ESSは、複数のBSSを連携させて構成される大規模な無線LANネットワークを意味します。ESSでは、複数のAPがそれぞれ異なるBSSを構成し、それらをDistribution System (DS) を介して接続することで1つの大きなネットワークを作ります。このDSは通常、有線LANが使用されますが、無線による接続も可能で、その場合はWireless Distribution System (WDS) と呼ばれます。ESS全体を識別するために使用される識別子がSSID (Service Set Identifier) であり、これは最大32文字までの英数字で表されます。同一のSSIDを持つAPは同じESSに属しているとみなされ、端末はこのSSIDを基準にネットワークを選択します。
ESSの特筆すべき点として、複数のAPで広いエリアをカバーできることや、ローミングによるシームレスな接続が可能である点があります。ローミングとは、端末が1つのBSSから別のBSSへ移動する際に、接続先のAPを自動的に切り替える仕組みです。この仕組みによって、ユーザーは移動しながらも通信が途切れることなく利用できます。また、ESSは同一空間内に複数構築することも可能であり、オフィスや学校といった大規模施設で複数のネットワークを共存させる設計が可能です。ただし、複数のESSやBSSを近接して配置する場合には、電波干渉を防ぐためにチャネル設定に十分な配慮が必要です。
このように、BSSは無線LANネットワークの最小単位であり、インフラストラクチャモードとアドホックモードの2つの形態が存在します。そしてESSは、複数のBSSを結合し、より広範囲でシームレスな通信を可能にする構成であり、SSIDやDSといった要素が重要な役割を果たします。