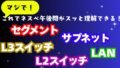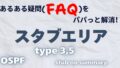1000BASE-LXって何?
1000BASE-LXは、IEEE 802.3規格に準拠したギガビットイーサネットの光ファイバー接続方式である。主な仕様は以下のとおり。
- 波長: 1310nm
- 対応ファイバー: シングルモードファイバー (SMF)、マルチモードファイバー (MMF)
- 最大伝送距離:
- SMF: 5,000m (5km)
- MMF: 550m
解説:
1000BASE-LXは長距離通信向けに設計されており、シングルモードファイバーを使えば最大5kmまで通信できます。ただし、マルチモードファイバーを使う場合、距離は550mまで短くなります。
マルチモードではモード分散(光の経路差による信号の広がり)が発生するため、長距離になると信号が劣化します。そのため、MMFを使う場合でも、短距離であれば1000BASE-LXを利用できます。

波長って何ですか?
波長(wavelength)は、光や電波などの波が 1回振動する長さ のことです。波には「山」と「谷」がありますが、山から次の山までの距離 を波長と呼びます。単位は ナノメートル (nm) や メートル (m) で表されます。
例えば、目に見える光(可視光)の波長はだいたい 380nm〜700nm くらいです。
ナノ(nano)は、10の-9乗 を表します。(例:1 nm=1×10−9 m=0.000000001 m)
- 青い光: 約 450nm
- 緑の光: 約 550nm
- 赤い光: 約 650nm
波長が短いほどエネルギーが強く、長いほどエネルギーは弱くなります。
光ファイバー通信における波長
光ファイバー通信では、電気信号を 光信号 に変換してデータを送ります。このとき使う光の波長がとても重要です。光ファイバー内での光の振る舞いや伝送特性は、波長によって変わります。
特に光ファイバー通信では、以下の波長帯域がよく使われます:
- 850nm: 短距離伝送、マルチモードファイバー(MMF)向け
- 1310nm: 中距離伝送、シングルモードファイバー(SMF)・マルチモードファイバー両方で使用
- 1550nm: 長距離伝送、シングルモードファイバー向け
これらの波長は、ファイバー内での信号減衰(光が弱くなること)や分散(信号が広がること)が少ないので、通信に適しています。
1000BASE-LXの1310nmとは?
1000BASE-LXは、波長 1310nm の光を使うギガビットイーサネット規格です。この波長を使う理由は次のとおりです。
- 減衰が低い: 光ファイバー内での光の損失が少なく、遠くまで届く。
- 分散が小さい: 信号の広がりが少なく、長距離でもデータの品質が保たれる。
- 長距離対応: シングルモードファイバーなら最大 5km、マルチモードファイバーなら最大 550m まで通信できる。
要するに、1310nmは「信号が劣化しにくく、長距離通信に向いている波長」 ということです!
まとめ
- 波長 は山から次の山までの距離 を波長
- 光ファイバー通信では、減衰や分散が少ない特定の波長(850nm, 1310nm, 1550nm)が使われる。
- 1000BASE-LXは1310nmの光を使い、長距離でも安定したギガビット通信ができる。

SMFとMMFって何?
シングルモードファイバー(SMF)は長距離伝送に優れているので、「じゃあ全部シングルモードでいいのでは?」と思いますよね?でも、実はシングルモードにもデメリットがあるので、ケースバイケースでマルチモードが選ばれることがあるんです。順番にわかりやすく見ていきましょう!
シングルモードファイバー (SMF) とは?
- 光の伝わり方: 1本の直進する光(モード)だけが伝搬
- コア径: 約 9μm(非常に細い)
非常に細いからこそ、光の反射する隙を与えず、1本の光として伝送することができる。 - 波長: 1310nm / 1550nm など
- 最大距離: 数km〜数十km以上(規格による)
- メリット:
- 減衰が少ない(信号が弱くなりにくい)
- 分散がほぼない(信号のズレが発生しにくい)
- 超長距離通信に対応可能
- デメリット:
- 光源(レーザー)が高価
- ファイバー自体も高価
- コアが細いため、接続や融着(ファイバーの接合)が難しく、作業コストやスキルが必要
つまり、シングルモードは「高性能だけど高価で扱いが難しい」んです。
マルチモードファイバー (MMF) とは?
- 光の伝わり方: 複数の経路(モード)で光がジグザグに進む
- コア径: 50μm or 62.5μm(太め)
太いことにより、光が反射する隙ができる。その結果、1本光ではなく、反射して複数の光になってしまう。 - 波長: 850nm / 1310nm など
- 最大距離: 数十m〜数百m程度
- メリット:
- 光源(VCSELなど)が安価
- ファイバーが安価
- コアが太いため、接続や融着が簡単
- デメリット:
- モード分散が発生しやすく、長距離で信号劣化
- 減衰もシングルモードより多い
つまり、マルチモードは「短距離ならコスパがよくて取り扱いやすい」んです。

MMFと大層な命名をされているので、意図して複数の光に分散させていると勘違いしないように!ただ、細いコア作成が技術的に困難であったため、太いコアにせざるを得なかった。その結果、光が複数に分散する。というニュアンスです!
なぜマルチモードがまだ使われるのか?
例えば、データセンターやオフィス内のフロア間接続 を考えてみましょう。
- 距離: 10m〜300m程度
- 必要な速度: 1Gbps〜10Gbps
- コスト意識: なるべく安く済ませたい
この場合、シングルモードを使うとオーバースペックになり、コストと手間がかかりすぎ ます。逆にマルチモードなら短距離なら十分な速度と安定性が得られるので、結果的にコスト最適化ができます。
まとめ
- シングルモード: 長距離・高性能だが高価&扱いが難しい → 長距離接続・外部回線・WAN向き
- マルチモード: 短距離・安価で扱いやすいが距離制限あり → 建物内・データセンター・LAN向き

モードコンディショニングパッチコード(MCP)って何?
「モード・コンディショニングパッチコード(Mode Conditioning Patch Cord, MCPC)」は、1000BASE-LX をマルチモードファイバー(MMF)で短距離接続するときに信号品質を保つために使われます。
なぜ必要なのか、そしてどう機能するのか、パパっと見ていきましょう!
なぜモード・コンディショニングパッチコードが必要なの?
1000BASE-LXはもともと シングルモードファイバー (SMF) を想定して設計されています。シングルモード用の送信機は、レーザー光 を使い、細いファイバーの真ん中をまっすぐ進むように光を出します。
でも、これをそのまま マルチモードファイバー (MMF) に流すと、次の問題が発生します。
- 差動モード遅延 (DMD): 光がMMFの中心部に強く集中すると、コアの内壁に反射する光と、中心を直進する光の間で伝搬速度に差が生まれます。その結果、信号が広がり、受信側でデータが乱れることがあります。
これが起こると、短距離でもパケットエラーが発生し、通信が不安定になります。
モード・コンディショニングパッチコードの役割
モード・コンディショニングパッチコードは、この DMD を防ぐための特殊な光ファイバーケーブルです。
仕組み:
- 片側: シングルモードファイバー (SMF)
- もう片側: マルチモードファイバー (MMF)
- 接続部分: 光の信号を 中心から少しずらして MMFに入射させる
これによって、光がファイバーの中心ではなく 少し外れた位置 から広がるので、複数の光経路が適度に混ざり、DMDの影響が軽減 されます。結果として、短距離でも安定した信号伝送が可能になります!
図解イメージ(簡単に言うと)
- 通常の接続: 光がファイバーの真ん中に集中 → モード遅延発生
- MCPC使用時: 光が中心から少しずれた位置に入射 → モード遅延が軽減
まとめ
- 問題: 1000BASE-LX を MMF で使うと、DMD が発生して信号劣化
- 解決策: モード・コンディショニングパッチコードを使う
- 効果: 光の入射位置をずらして、モード遅延を軽減 → 信号が安定

要するに、直進する光があると、到着に差がでるから、入射角をずらして直進する光を減らそうねっていう技術です。

MCPの両端でモード違うのはどういうこと?
MCPは、シングルモードファイバー(SMF)とマルチモードファイバー(MMF)を途中でつなぎ合わせた特殊なケーブル です。
✅ 両端でモードが違うのはなぜ?
1000BASE-LXは、本来シングルモードファイバー(SMF)で使うレーザー光を、短距離ではマルチモードファイバー(MMF)で使おうとします。
問題点:
- シングルモードのレーザー光は、超細いSMF(コア9μm)を通るので、まっすぐ進む性質 を持つ
- でも、それをいきなり太いMMF(コア50μm or 62.5μm)に入れると、直進光がそのままMMFの中心を突き抜けてしまい、モード分散がひどくなる
この「いきなり太いMMFに入れると直進光が発生する」問題を解決するために、MCPは 「途中にSMFを少しだけ入れて、光の角度を調整する」 という工夫をしています。
✅ どうやって「片側SMF・片側MMF」になってるの?
MCPは、片側はSMF(シングルモードファイバー)、もう片側はMMF(マルチモードファイバー)になっていますが、これは 「途中でSMFとMMFを融着(接続)」 しているからです!
具体的な構造
- 片側(機器側) → シングルモードファイバー(SMF、コア9μm)
- 途中でSMFとMMFをつなぐ(融着接続)
- もう片側(ネットワーク側) → マルチモードファイバー(MMF、コア50μm or 62.5μm)
✅ コア径が違うのに、どうやってつなぐの?
「SMFはコアが9μm、MMFは50μmや62.5μmなのに、どうやって接続してるの?」という疑問が出ますよね。
ここがMCPの 最大の工夫ポイント です!
ポイント①:SMFの出口をMMFの中心から少しズラす!
普通にど真ん中にSMFを接続すると、直進する光がそのまま出ちゃいます。
そこで、SMFの出口を少しズラして、MMFのコアの端っこの方に光を入れるようにする んです。
✅ こうすると、光がMMFに入るときに最初からちょっと傾いた角度になるので、直進光が減って、適度に反射する光になり、モード分散が減ります。
ポイント②:徐々に太いファイバーに移行することで、光のロスを最小限にする!
いきなり細いSMF(9μm)から太いMMF(50μm or 62.5μm)に繋ぐと、光のロスが大きくなります。
そのため、SMFとMMFを滑らかにつなげる 「テーパー状の接続」 をすることで、光がスムーズに移行するように工夫されています。
✅ MCPの動作まとめ
- シングルモードレーザーの光を、まずSMFで通す
- ここでは通常のシングルモード光が出る
- 途中でSMFをMMFにズラして接続
- これによって、直進する光を抑えて、適度に反射する光だけがMMFに入るようにする
- その後、MMFで普通に通信
- 直進光が抑えられているので、モード分散の影響が減る
✅ 結局、「片側SMF・片側MMF」って何がしたいの?
- 1000BASE-LXのレーザーは 本来SMF用
- でも、短距離ではコストの問題で MMFを使いたい
- いきなりMMFに入れると直進光が発生してしまうので、それを減らすために「一度SMFを通して角度を調整する」
- だから、MCPは 「片側はSMF」「途中でMMFにズラして接続」「もう片側はMMF」 という構造になっている
✅ まとめ
- MCPは、途中でSMFとMMFを接続している特殊なケーブル!
- SMF → MMFに光を入れるときに、中心をズラして直進光を抑える!
- 結果的に、1000BASE-LXをMMFで安定して使えるようになる!

MCPはデファクトスタンダード的な技術なの?
MCPは 「1000BASE-LX をマルチモードファイバー(MMF)で使うときに発生する問題を解決する手段の1つ」 です。ただし、今ではそこまで一般的に使われているわけではなく、「必要な場面では使うが、なるべく避ける」という感じになっています。
✅ MCPはどんな場面で使われるのか?
MCPは、「1000BASE-LX を MMF で使いたいけど、モード分散の影響を抑えたい!」 というときに使います。
でも、そもそも「1000BASE-LXをMMFで使う」こと自体があまり推奨されていません。
(1)MCPを使う場面
- 企業のネットワークなどで「すでにMMFの配線がある」けど「スイッチを1000BASE-LX対応のものに変えたい」とき
- すでにMMFが敷設されているなら、なるべくそのまま使いたい
- でも1000BASE-LXの光源はシングルモード用なので、そのままMMFに入れると問題が起こる
- だからMCPを使って調整する
(2)MCPを使わない方法(最近の主流)
そもそも最初から1000BASE-SX(850nmのMMF用規格)を使う
- 1000BASE-SXは最初からMMF用に設計されているので、MCPを使う必要がない
- しかもMCPを使うよりも安価でシンプルに運用できる
このため、新規にネットワークを構築する場合、MCPを使うよりも 最初から1000BASE-SXを選ぶ ことが多いです。
✅ MCPを使うとコストは高くなる?
✅ 結論:MCPを使うとコストが高くなる!
理由は以下の通りです。
- MCP自体が普通のMMFパッチコードより高い
- MCPはSMFとMMFを特殊な方法で接続したケーブルなので、普通のMMFパッチコードより高価
- MCPを使うことで運用が複雑になる
- 接続方法を間違えると正しく動作しない(SMF側とMMF側を間違えたら意味がない)
- MCP対応の光モジュールが必要 になる場合もある
- だったら最初から1000BASE-SX(MMF用)を選んだ方がコストが安い
- MCPを買うくらいなら、最初から1000BASE-SXにした方が安くてシンプル
このため、新規導入ならMCPをわざわざ選ぶことは少ないです。
✅ じゃあMCPは常識的に使うものなのか?
「MCPを使うのが常識」というわけではない!
むしろ、以下のような感じで考えられています。
- 新しくネットワークを作るなら、MCPを使わないのが普通
- 1000BASE-SX(MMF用) や 1000BASE-LXをSMFで使う のが一般的
- つまり、MCPを使わない設計が最適
- でも、既存のMMF配線をそのまま使いたいなら、MCPを使うこともある
- 既存のMMFを活かして1000BASE-LXを導入する場合、MCPを使うのが一つの手段
- ただし、この場合も「そもそもMMFで1000BASE-LXを使うのが正解なのか?」を検討する必要がある
✅ まとめ
- MCPは「1000BASE-LXをMMFで使うときの問題を解決する手段」
- ただし、「1000BASE-LXをMMFで使う」こと自体があまり推奨されていない
- MCPを使うとコストが高くなる(パッチコード自体の価格、運用の複雑さ)
- そのため、普通は 1000BASE-SX(MMF用)を使うか、1000BASE-LXをSMFで使う のが一般的
- 新規導入ではMCPを使わないのが主流
- 「MCPを使うのが常識」というわけではなく、「必要な場面で仕方なく使う技術」
- つまり、知識のある人が「仕方なく」使うことはあるが、そもそも使わない方がいい
結論として、MCPは「必ず使うもの」ではなく、「過去の設備(MMF)をそのまま使いたいときの選択肢の1つ」っていう立ち位置ですね!

1000BASE-LX以外の有線LANの規格は?
| 規格名 | 最大速度 | 伝送媒体 | 最大距離 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|---|
| 100BASE-TX | 100Mbps | UTP(Cat5以上) | 100m | ファストイーサネット(現在はあまり使われない) |
| 1000BASE-T | 1Gbps | UTP(Cat5e以上) | 100m | 現在の主流(ギガビットイーサネット) |
| 1000BASE-TX | 1Gbps | UTP(Cat6以上) | 100m | 1000BASE-Tより配線しやすいが普及せず |
| 10GBASE-T | 10Gbps | UTP(Cat6a以上) | 100m | 企業やデータセンター向け(レイテンシが若干高い) |
| 1000BASE-LX | 1Gbps | SMF, MMF | 5km(SMF) 550m(MMF) | シングルモード中心、長距離通信可能 |
| 1000BASE-SX | 1Gbps | MMF | 550m | 近距離向け光ファイバー規格 |
| 10GBASE-LR | 10Gbps | SMF | 10km | 長距離光ファイバー通信 |
| 10GBASE-SR | 10Gbps | MMF | 300m | 短距離の光ファイバー通信 |
| 25GBASE-T | 25Gbps | UTP(Cat8) | 30m | 企業・データセンターでの次世代LAN |
| 40GBASE-SR4 | 40Gbps | MMF | 100m | データセンター向け、高速短距離通信 |
| 100GBASE-LR4 | 100Gbps | SMF | 10km | 超高速バックボーン向け |
✅ 試験に出やすいポイント
- 1000BASE-T vs 1000BASE-LX/SX の違い
- 1000BASE-T:銅線(UTP)、最大100m
- 1000BASE-LX:シングルモード光ファイバー(SMF)、最大5km
- 1000BASE-SX:マルチモード光ファイバー(MMF)、最大550m
- 10GBASE-T と 10GBASE-SR/LR の違い
- 10GBASE-T:ツイストペアケーブル(Cat6a)、最大100m
- 10GBASE-SR:マルチモード光、最大300m
- 10GBASE-LR:シングルモード光、最大10km
- 「BASE-T」 vs 「BASE-SX/LX/LR」
- 「-T」 はツイストペアケーブル(UTP)
- 「-SX/LX/LR」 は光ファイバー
- PoE(Power over Ethernet)との関係
- 1000BASE-Tや10GBASE-T はPoEに対応できるが、光ファイバーはPoE不可
✅ まとめ
- 1000BASE-T(UTP) vs 1000BASE-LX(光) の違いを理解する
- 10GBASE-Tと10GBASE-SR/LRの用途の違いを押さえる
- ツイストペア vs 光ファイバーのメリット・デメリットを整理する

有線LAN以外でネスペに頻出する規格は?
| 分類 | 規格・技術 | 説明・ポイント |
|---|---|---|
| 有線LAN | 100BASE-TX | – 100Mbpsのツイストペアケーブル用規格(カテゴリ5以上) |
| 1000BASE-T | – 1Gbpsのツイストペアケーブル用規格(カテゴリ5e以上) | |
| 1000BASE-LX | – 光ファイバーを用いる1Gbps規格(SMFで最大5km, MMFで最大550m) | |
| 1000BASE-SX | – マルチモードファイバー(MMF)用の1Gbps規格(最大550m) | |
| 10GBASE-T | – 10Gbpsのツイストペアケーブル用規格(カテゴリ6a以上) | |
| PoE(IEEE 802.3af/at/bt) | – LANケーブルで電力供給が可能(PoE:最大15.4W、PoE+:最大30W、PoE++:最大60~90W) | |
| 無線LAN | IEEE 802.11a | – 5GHz帯、最大54Mbps |
| IEEE 802.11b/g | – 2.4GHz帯、bは最大11Mbps、gは最大54Mbps | |
| IEEE 802.11n | – 2.4GHz/5GHz帯、MIMO対応、最大600Mbps | |
| IEEE 802.11ac | – 5GHz帯、最大6.9Gbps(理論値)、MU-MIMO対応 | |
| IEEE 802.11ax | – 6GHz帯(Wi-Fi 6E)、OFDMA対応、最大9.6Gbps | |
| WAN(広域網) | PPP(Point-to-Point Protocol) | – シリアル通信やVPNで使われる基本的なデータリンクプロトコル |
| PPPoE(PPP over Ethernet) | – フレッツ光などで使われる、Ethernet上でPPPをカプセル化する技術 | |
| MPLS(Multi-Protocol Label Switching) | – パケット転送を高速化するためのラベルスイッチング技術 | |
| SD-WAN | – ソフトウェア制御でWANを仮想化し、回線コストを最適化する技術 | |
| ルーティング | RIP(Routing Information Protocol) | – 伝統的な距離ベースのルーティングプロトコル(最大ホップ数15) |
| OSPF(Open Shortest Path First) | – 階層型のリンクステートルーティングプロトコル | |
| BGP(Border Gateway Protocol) | – インターネットの経路制御に使われるAS間ルーティングプロトコル | |
| スイッチング | VLAN(仮想LAN) | – 物理ネットワークを仮想的に分割し、ブロードキャストを制御 |
| STP(Spanning Tree Protocol) | – ループを防ぐためのプロトコル(RSTP, MSTPも) | |
| LACP(Link Aggregation Control Protocol) | – 複数の物理リンクを束ねて帯域幅を増強する技術 | |
| セキュリティ | IEEE 802.1X | – ポートベースの認証プロトコル(RADIUSと連携) |
| MACアドレスフィルタリング | – 許可されたMACアドレスだけ通信を許可 | |
| IPsec(Internet Protocol Security) | – VPNなどで使われる暗号化技術(AH/ESP) | |
| TLS(Transport Layer Security) | – HTTPSやVPNで使われる暗号化プロトコル | |
| 仮想化・クラウド | VXLAN(Virtual Extensible LAN) | – VLANの拡張版、オーバーレイネットワーク技術 |
| SDN(Software-Defined Networking) | – ネットワーク制御をソフトウェアで行う技術 | |
| NFV(Network Functions Virtualization) | – ルーターやファイアウォールを仮想化 | |
| 監視・運用 | SNMP(Simple Network Management Protocol) | – ネットワーク機器を監視するためのプロトコル |
| NetFlow | – ルータやスイッチのトラフィック監視技術 | |
| Syslog | – ネットワーク機器のログを集約・管理する仕組み |
✅ どういう風に試験に出るの?
- 1000BASE-LX と 1000BASE-SX の違いを問う問題
- STPやLACPの動作を問う問題
- IPsecやTLSなどの暗号技術を組み合わせる問題
- SDN/NFVを絡めた最新技術に関する問題
- MPLSやBGPなどのWANの設計を問う問題
✅ まとめ
- 試験では、物理層(LAN/WAN)からアプリケーション層(セキュリティ・仮想化)まで幅広く出題される
- 1000BASE-LXや1000BASE-Tのような通信規格だけでなく、ルーティング・スイッチング・セキュリティ技術も重要
- 実際の問題では、複数の技術を組み合わせたシナリオ問題が多いので、単純な暗記ではなく「どう活用するか」を理解するのが大事